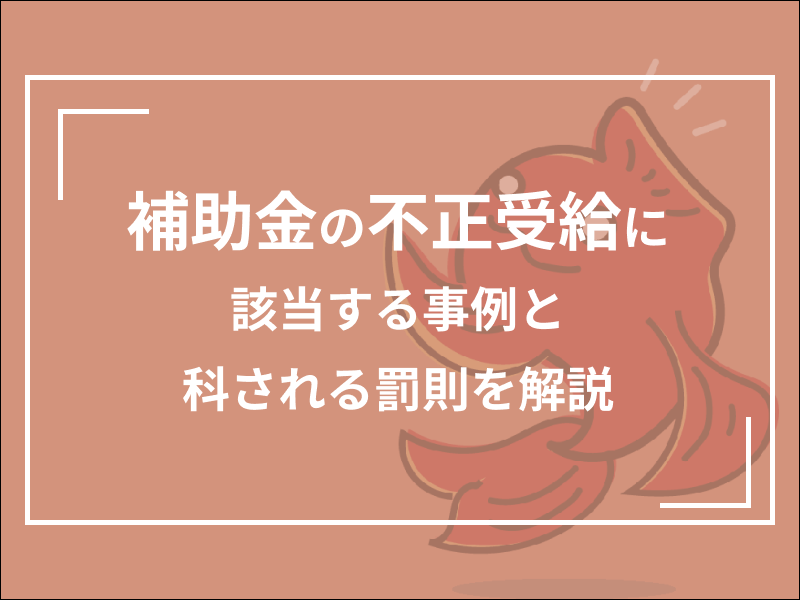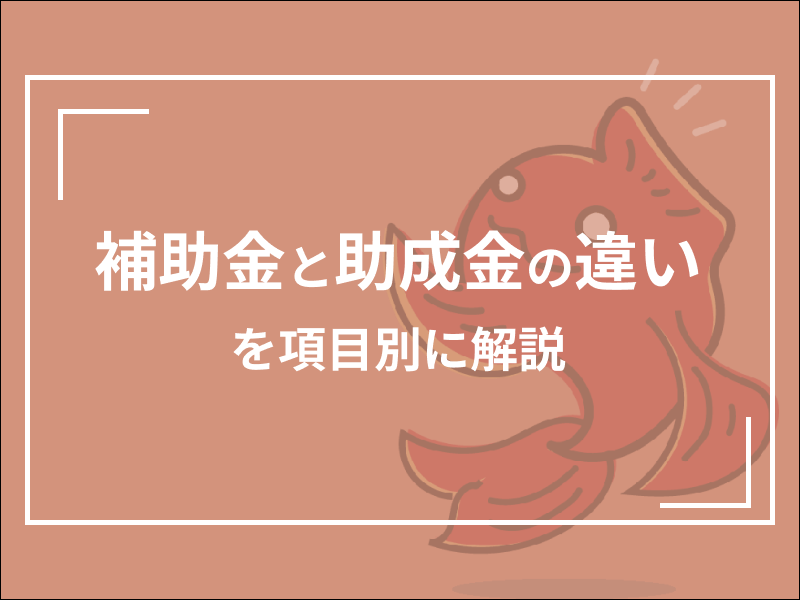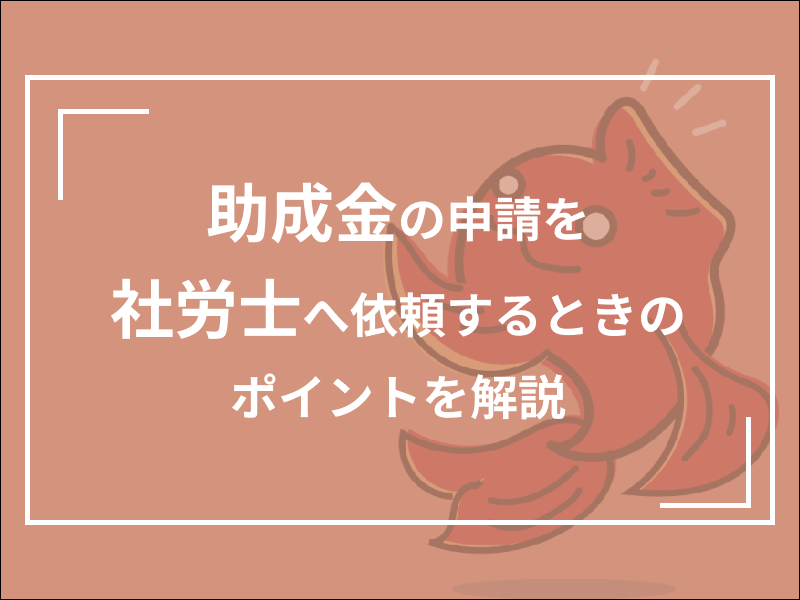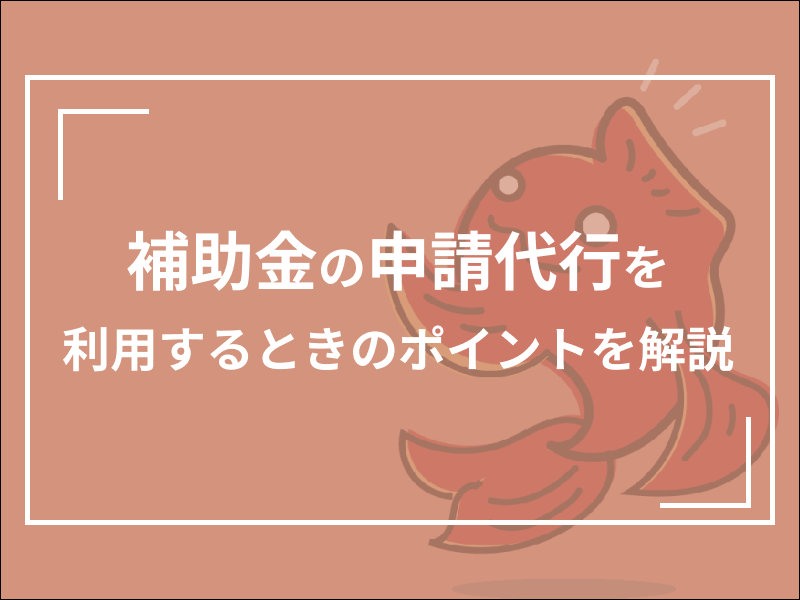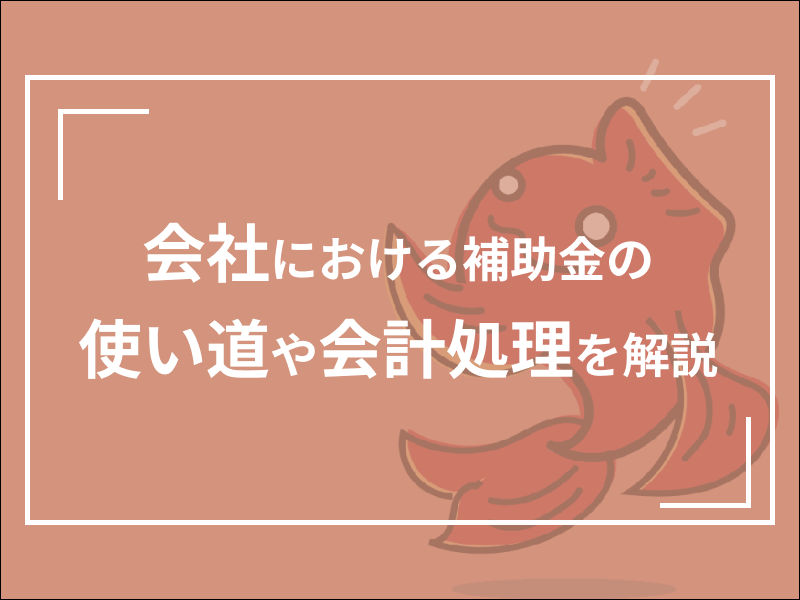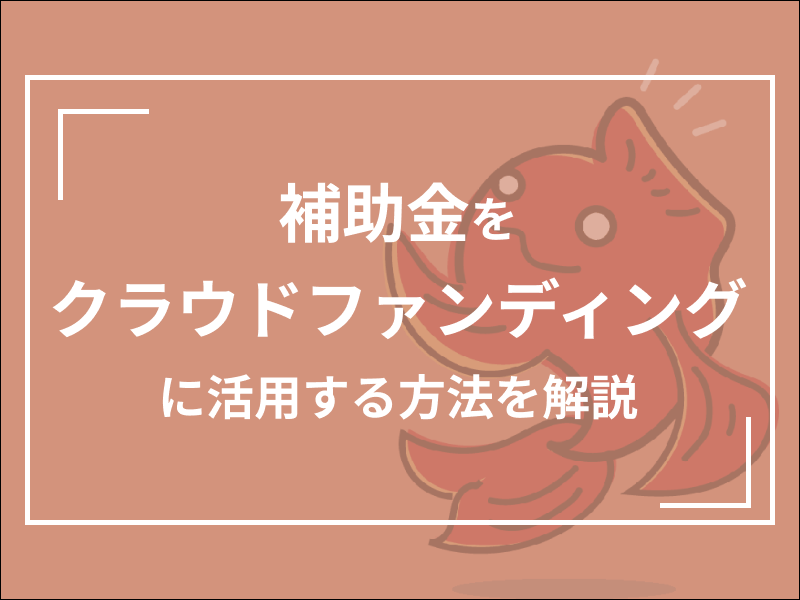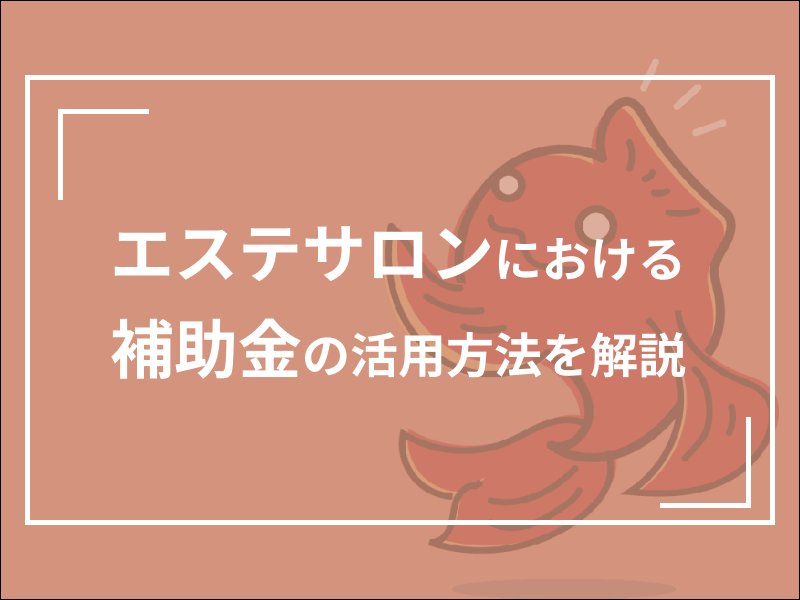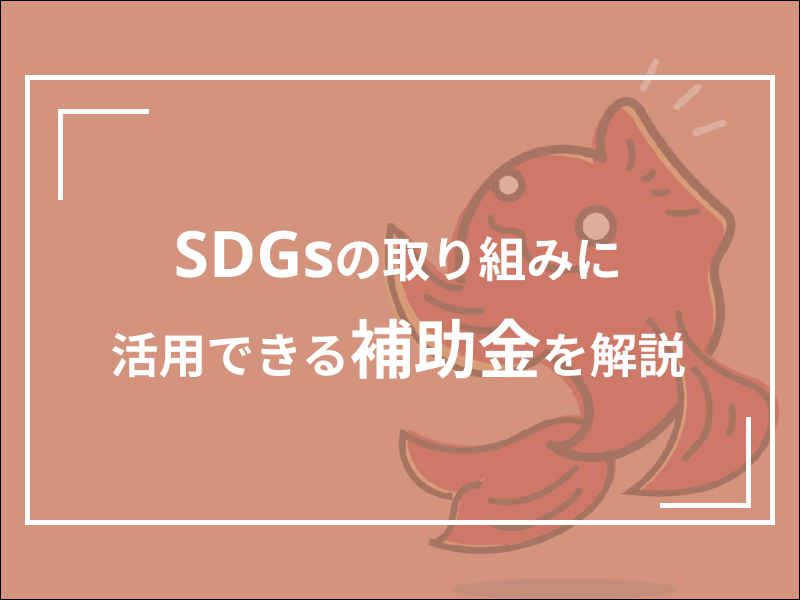
SDGsの取り組みに活用できる補助金を解説
事業者向けの補助金の中で、「SDGs」を実現するための取組に活用できる制度があります。「SDGs」とは、環境、差別、貧困といった世界のさまざまな課題を解決し、より良い世界をつくるために設けられた世界共通の17の目標のことです。
当記事では、SDGsの取組に活用できる補助金を解説します。補助金を活用してSDGsの取組を行うことを検討している人は参考にしてみてください。
補助金を活用して取り組めるSDGsの目標がある
補助金を活用して取り組めるSDGsの目標があります。まずは、SDGsの17の目標における取組例を把握した上で、補助金をどのように活用できるのか確認してみましょう。
|
SDGsの目標 |
取組例 |
|
目標1 貧困をなくそう |
自立支援、無償の医療支援 等 |
|
目標2 飢餓をゼロに |
子ども食堂、栄養改善の支援 等 |
|
目標3 すべての人に健康と福祉を |
感染症対策に向けて製品開発 等 |
|
目標4 質の高い教育をみんなに |
教育支援 等 |
|
目標5 ジェンダー平等を実現しよう |
労働環境改善、社内託児所の開設 等 |
|
目標6 安全な水とトイレを世界中に |
節水設備の導入、途上国にトイレを提供 等 |
|
目標7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに |
再生可能エネルギー発電設備の導入、持続可能なエネルギーの開発 等 |
|
目標8 働きがいも経済成長も |
働き方改革 等 |
|
目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう |
インフラ整備 等 |
|
目標10 人や国の不平等をなくそう |
労働環境改善、障がい者雇用 等 |
|
目標11 住み続けられるまちづくりを |
防災への取組 等 |
|
目標12 つくる責任つかう責任 |
リサイクル可能な素材の使用、食品ロスの削減対策 等 |
|
目標13 気候変動に具体的な対策を |
省エネ設備導入、環境に配慮した製品開発 等 |
|
目標14 海の豊かさを守ろう |
海洋汚染対策、プラスチックごみの削減の取組 等 |
|
目標15 陸の豊かさも守ろう |
植樹活動の取り組み、持続可能な森林経営 等 |
|
目標16 平和と公正をすべての人に |
労働環境改善、学習支援事業 等 |
|
目標17 パートナーシップで目標を達成しよう |
国際交流に係る取組 等 |
参考:SDGs17の目標|SDGsクラブ(公益財団法人日本ユニセフ協会)
たとえば、中小企業における働き方改革を目的とする補助金があります。働き方改革への取り組みは持続可能な経済成長が期待できるため、SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」の達成につながる可能性があります。
また、カーボンニュートラルの実現を目的とした補助金があります。カーボンニュートラルの実現に向けた取組は、脱炭素化が期待できるため、SDGsの目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」やSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」の達成につながります。
なお、補助金によってはSDGsの目標の中で、複数の目標達成を目指す取組が必要となる場合があります。自社が達成を目指せる目標を指定しているかどうか、補助金の公式サイトにて確認しておきましょう。
エネルギーをみんなにそしてクリーンに
SDGsの目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」の取組に活用できる補助金があります。補助金を活用して目標達成を目指すことで、エネルギー問題の解決につながります。
【補助金を活用したSDGsの目標達成に向けた取組例】
- 再生可能エネルギー発電設備の導入
- 省エネ設備導入 等
たとえば、再生可能エネルギー発電設備の導入に利用できる補助金があります。太陽光発電設備などを導入することにより、発電時に地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑えられることから、SDGsの目標の施策「事業活動で使用する電力を再生可能エネルギーに切り替え」を実施できます。
また、省エネ設備導入に利用できる補助金があります。省エネ設備導入を導入することによりエネルギーの消費量を減らし、エネルギー効率の向上につながることから、SDGsの目標の施策である「二酸化炭素(CO2)の排出量を抑えること」を実施できます。
SDGsの目標のひとつである「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」のための取組には、再生可能エネルギー設備の導入や省エネ設備の導入などがあります。省エネ設備を導入することによって、二酸化炭素の排出量を削減し、地球温暖化の抑制につながるでしょう。
働きがいも経済成長も
SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」の取り組みに活用できる補助金があります。「働きがいも経済成長も」は、持続可能な経済成長および誰もが平等に働きがいを持ち、人間らしい働き方(ディーセント・ワーク)の実現が目的で設定された目標です。
【補助金を活用したSDGsの目標達成に向けた取組例】
- 労働時間の短縮
- 最低賃金の引き上げ
- 雇用環境や業務体制整備
- 研修制度の導入
- 処遇の改善 等
たとえば、労働管理ソフトの導入費用の一部が支援される補助金があります。労務管理ソフトの導入により業務効率化が可能となることから、労働時間の短縮や従業員のモチベーション向上につながり、働きがいのある人間らしい仕事(ディーセントワーク)を実現できます。
また、社内などで実施した研修にかかる費用の一部が支援される補助金があります。研修制度を導入することで、従業員のスキルが向上し、平等に活躍できる職場となり、SDGsの施策である「労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進」につながります。
補助金を活用して、「働きがいも経済成長も」の取組を行うことで、自社の抱える労働環境の問題を解決できる場合があります。従業員が働きやすい職場環境づくりに取り組むことにより、従業員の働きがいが向上し、離職率の低下につながる可能性があります。
産業と技術革新の基盤をつくろう
SDGsの目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の取組に活用できる補助金があります。「産業と技術革新の基盤をつくろう」は、暮らしを支えるインフラを整え持続可能な産業の発展と技術革新の促進という目的のもと、設定された目標です。
【補助金を活用したSDGsの目標達成に向けた取組例】
- 資源利用効率が向上する生産方法の改善
- 環境に配慮した技術・産業方法を導入
- 廃棄物の発生を抑える製品を開発 等
たとえば、SDGsの目標に向けて新製品を開発する際にかかる費用の一部が支援される補助金があります。資源を繰り返し利用するための装置を導入することで、限られた資源の使用量を抑えられ、環境に配慮した生産方法を取り入れることができ、持続可能な産業化につながる可能性があります。
また、再生可能エネルギーを活用する機械の開発費などの一部が支援される補助金があります。再生可能エネルギーを活用する機械の開発を行うことで、クリーンで環境に配慮した技術や産業方法を取り入れることができ、技術革新の促進につながる可能性があります。
補助金を活用して、生産方法の改善や技術を開発することによって業務の効率化にも取り組めます。業務効率化となるほかに、生産方法の改善を行い資源を繰り返し利用する場合、資源にかかるコストを削減することができます。
住み続けられるまちづくりを
SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」の取り組みに活用できる補助金があります。「住み続けられるまちづくりを」は、地域の過疎化や環境問題を解決し、誰もが安全で快適に暮らし続けられるまちをつくることを目標としています。
【補助金を活用したSDGsの目標達成に向けた取組例】
- 地域活性化を促進する事業
- 雇用機会が特に不足している地域での事業所の設置や従業員の雇用
- 再生可能エネルギー発電設備の導入
- 省エネ設備導入 等
たとえば、補助金を活用して、雇用機会が特に不足している地域に事業所を設置し従業員を雇用することができます。地域に事業所を設置し雇用機会を創出することにより、地域の過疎化を防ぎ、人手を増やすことができるため従業員の負担を軽減できる可能性があります。
また、補助金を活用して、再生可能エネルギー発電設備を導入することができます。再生可能エネルギー発電設備を導入することにより、環境に配慮したエネルギーに切り替えられ「住み続けられるまちづくりを」に挙げられている大気汚染の問題の解決につながります。
SDGsの目標のひとつである「住み続けられるまちづくりを」の取組には、人材雇用や省エネ設備の導入などがあります。補助金を活用して人材雇用や省エネ設備の導入を行うことで、事業所が抱える人手不足などの問題解決やエネルギーコスト削減につながる可能性があります。
つくる責任つかう責任
SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」の取組に活用できる補助金があります。「つくる責任つかう責任」は、持続可能な消費と生産を目指した目標です。
【補助金を活用したSDGsの目標達成に向けた取組例】
- フードロスの削減につながる機械装置の開発
- 資源を長期的に使用できるものにする取組
- 廃棄物リサイクル 等
たとえば、急速冷凍機の開発費用の一部が支援される補助金があります。急速冷凍機を開発することで、解凍後でも冷凍前と変わらない品質を維持することができ、長期保存が可能となるためフードロスの削減につながります。
また、花をドライフラワーにする機械装置の導入費用の一部が支援される補助金があります。ドライフラワーにすることで、生花の廃棄を減らすことができ、コストの削減や持続可能な消費を可能にすることができます。
補助金を活用することにより、費用を抑えて廃棄を減らすための機械装置導入や技術開発に取り組むことが可能です。フードロスや資源廃棄の削減に取り組むことは、SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」の実現につながるでしょう。
SDGsの取組に活用できる補助金の具体例
国や自治体が実施する補助金の中には、SDGsの取組に活用できる制度があります。それぞれの補助金は、管轄や活用する用途などが異なることに留意しておきましょう。
|
補助金名 |
特徴 |
|
(環境省) |
省エネ設備導入・脱炭素目的の燃料転換を伴う設備導入等に要する費用の一部を支援する補助金 |
|
(経済産業省) |
新分野展開、業態転換、事業・業種転換等といった事業再構築の取組にかかる費用の一部を支援する補助金 ※低炭素技術の活用等を行った場合、書面審査にて加点される可能性あり |
|
(東京都) |
SDGs債の発行支援を行う事業に要する経費の一部を補助する制度 ※環境省が実施する指定補助金の交付決定を受けた者のみが申請者として認められる |
|
(愛知県) |
再生可能エネルギー発電設備等を導入する費用の一部を支援する補助金 |
|
(岐阜県) |
SDGs推進ネットワークの会員が実施するSDGsの普及啓発の取組に要する費用の一部を支援する補助金 |
|
(京都京丹後市) |
SDGsの達成および脱炭素社会実現に寄与する環境・経済・社会の3側面の課題に総合的に取り組む事業に対し費用の一部を支援する補助金 |
|
(群馬県) |
SDGsの目標8・9・11・12を対象とした取組に要する費用の一部を支援する補助金 |
|
(広島県福山市) |
SDGsの目標の視点を踏まえて行う新製品開発にかかる経費の一部を補助する制度 |
|
(厚生労働省) |
育児休暇や介護休業などの制度の導入といった就業環境整備に取り組む際にかかる費用の一部を支援する制度 |
|
(厚生労働省) |
労働時間短縮等を行った際にかかる就業規則・労使協定の作成・変更等の費用の一部を支援する制度 |
たとえば、環境省が運営する「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」では、4つの申請事業に分かれています。それぞれ申請要件は異なり、電化・脱炭素燃転型では、指定設備の中で電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備導入などの費用の一部が補助されます。
また、東京都が運営する「SDGs債発行支援事業補助金」は、SDGs債発行時の発行支援を行う事業に要する経費の一部を補助する制度です。SDGs債とは、SDGsの目標達成に貢献する事業の資金調達のために発行される債券のことです。
SDGsの取組に活用できる補助金には、SDGsの目標を達成することを目的に設けられた制度のほか、省エネ化や脱炭素の取組を支援し、結果としてSDGsの実現につながる制度もあります。補助金を活用して、SDGsの取組を行う場合、自社に合った補助金があるのかどうか探してみましょう。
まとめ
事業者向けの補助金の中には、SDGsの目標達成に貢献する取組に活用できる制度があります。SDGsとは、より良い世界をつくるために設けられた世界共通の17の目標のことです。
SDGsの目標はおもに環境、差別、貧困といった世界にある課題を解決するためであり、各目標はそれぞれ目標の内容が異なっています。日本の企業でも、補助金を活用して自社が抱える課題を解決しながらSDGsの目標達成に貢献することが可能です。
事業者向けの補助金には、国や自治体が実施する制度があります。それぞれ活用できる用途や申請要件などが異なるため、SDGsの取組に活用できる自社に合った補助金を選びましょう。