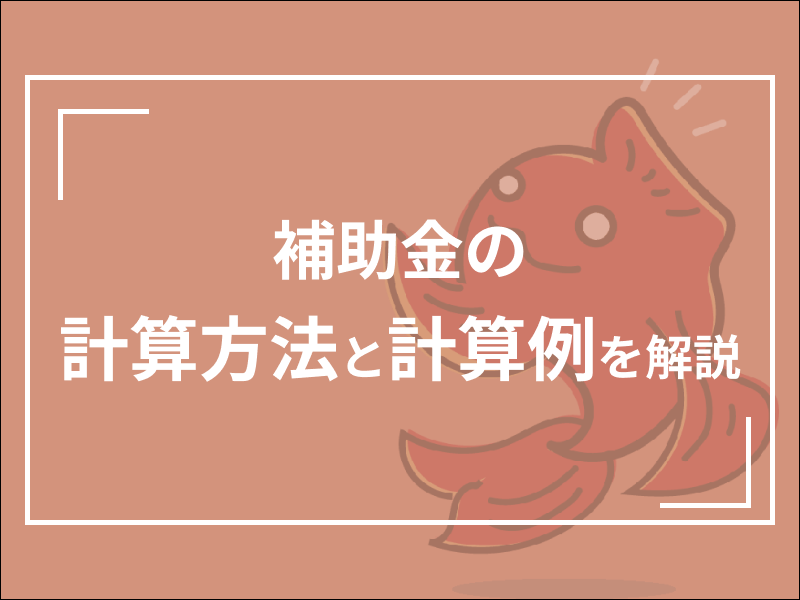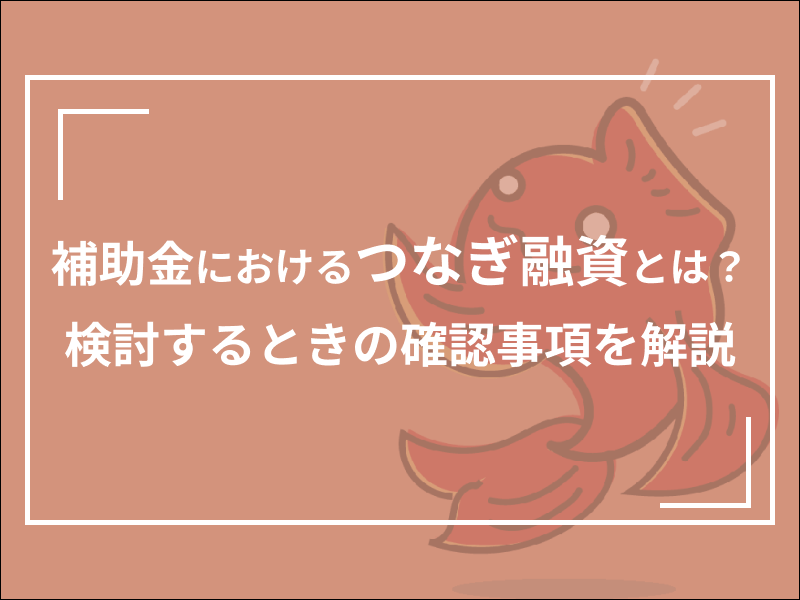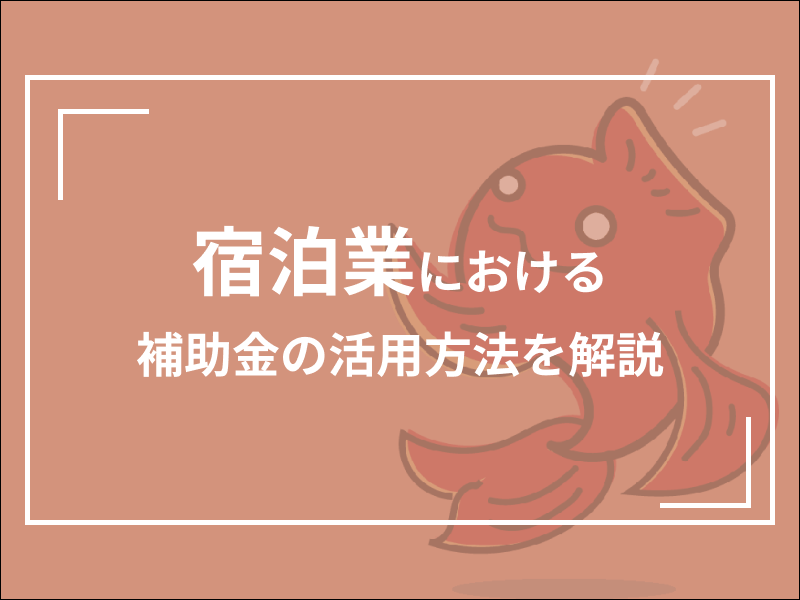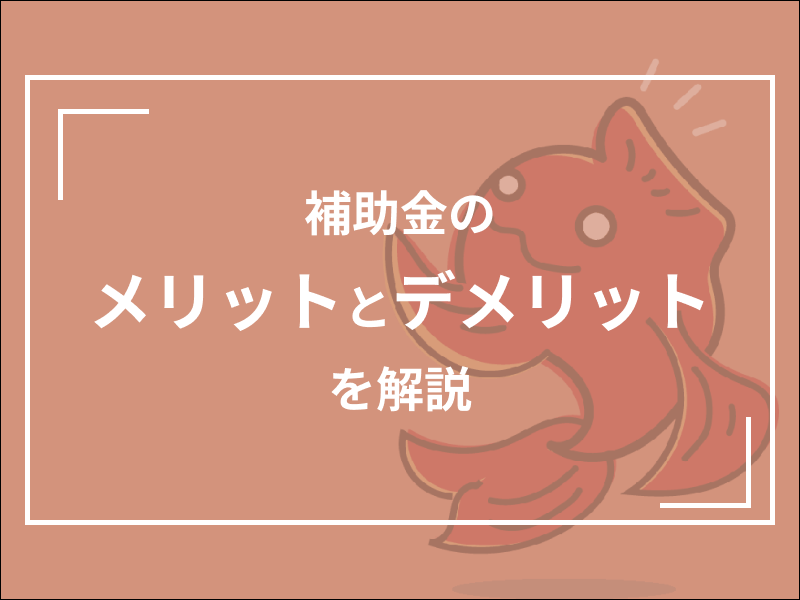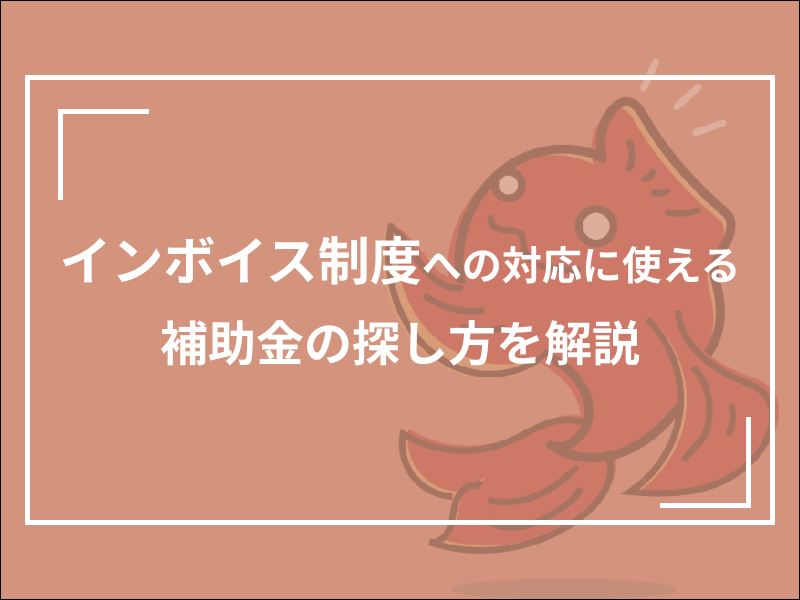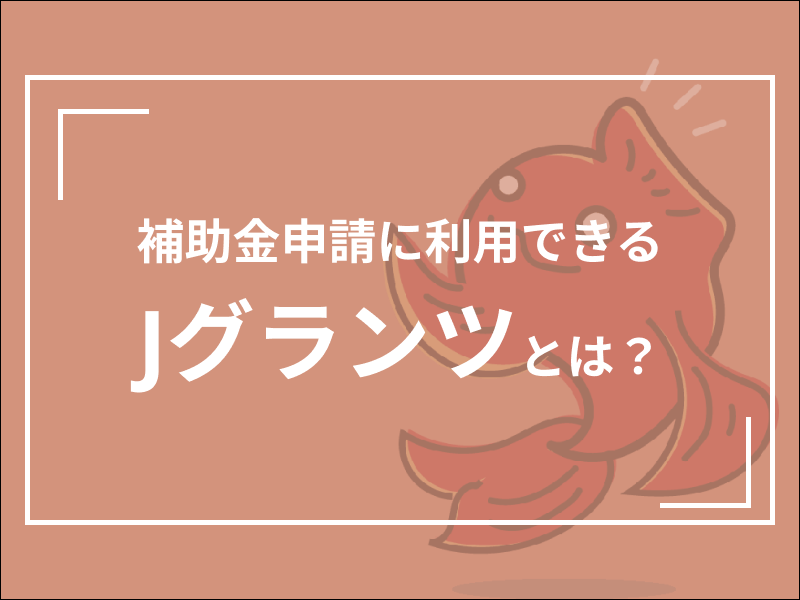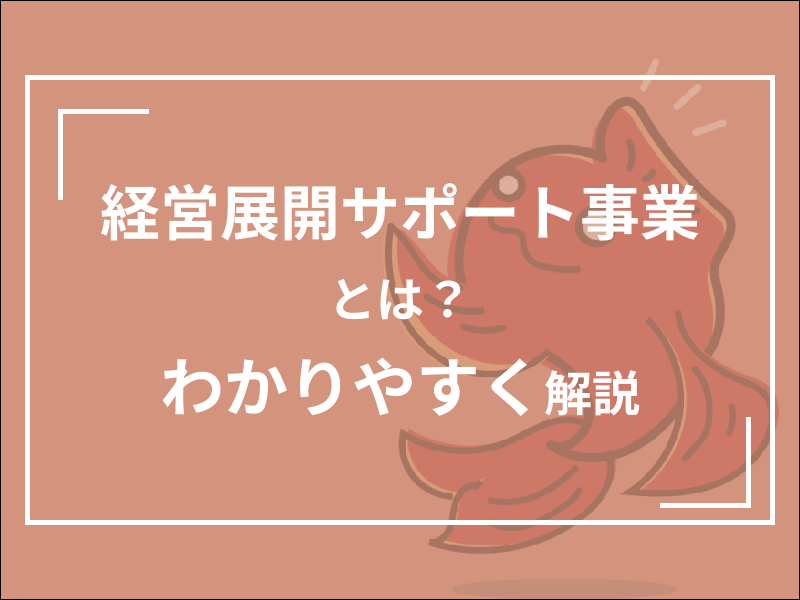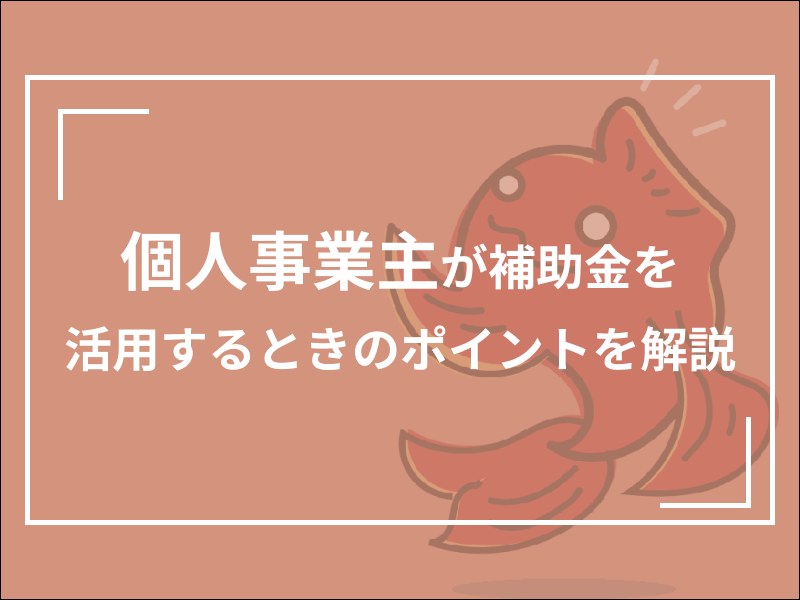ポストコロナにおける事業環境の変化に対応するため、国や地方自治体においてさまざまな支援制度が実施されています。東京都の事業者が利用できる支援制度のひとつとして、2024年度から募集が開始された助成金制度が「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(以下、経営展開サポート事業)」です。
当記事では、経営展開サポート事業とはどのような制度なのかを、はじめて申請する人向けにわかりやすく解説します。経営展開サポート事業の概要を知りたい人や、申請を検討している人は参考にしてみてください。
なお、当記事は経営展開サポート事業の公式サイトおよび「助成金 募集要項(一般コース)令和6年度第5回」をもとに作成しています。
経営展開サポート事業とは経営基盤の強化につながる取組を支援する制度
経営展開サポート事業とは、中小企業等の経営基盤の強化を図る取り組みを支援する助成金制度です。ポストコロナにおける消費者ニーズの変化や物価・エネルギー価格の高騰などに対応するため、これまで営んできた事業の「深化」や「発展」につながる事業が助成対象となります。
【経営展開サポート事業の概要】
|
項目
|
詳細
|
|
目的
|
中小企業等が既存事業を深化・発展させる計画を支援することにより、都内中小事業者の経営基盤を強化すること
|
|
対象事業
|
既存事業の「深化」または「発展」につながる事業
|
|
対象者
|
東京都内で事業を行う中小企業者(個人事業主を含む)
|
|
対象経費
|
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費
- 産業財産権出願・導入費
- 規格等認証・登録費
- 設備等導入費
- システム等導入費
- 専門家指導費
- 不動産賃借料
- 販売促進費
- その他経費
|
|
助成率
|
2/3以内
|
|
助成上限額
|
800万円
|
|
助成期間
|
交付決定日から最大1年間
|
経営展開サポート事業の助成対象者は、東京都内で事業を行う中小企業や個人事業主です。飲食業、サービス業、建設業、製造業など業種を問わずに利用できる助成金であり、令和6年4月から募集が行われています。
また、経営展開サポート事業の助成対象経費は、外部専門家に対する謝金や交通費を含む「専門家指導費」や、WEBサイト構築費を含む「販売促進費」など、既存事業を深化・発展させるために直接必要な経費です。取り組む事業において必要であると認められる場合に、最大800万円が助成されます。
経営展開サポート事業とは、新型コロナウイルスの影響やその後の物価高騰など、事業環境の激変に対応し、経営基盤の強化を図る中小企業を支援するために東京都が実施している助成事業です。経営展開サポート事業の概要は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が公開しているチラシからも確認できます。
対象事業
経営展開サポート事業に申請するためには、対象事業の要件を満たす必要があります。取り組もうとする事業が対象事業の要件を満たしていない場合は申請ができないため、経営展開サポート事業への申請を検討している人はその前提を踏まえておきましょう。
【経営展開サポート事業における対象事業】
|
事業内容
|
具体例
|
対象可否
|
|
既存事業の「深化」
|
|
〇
|
|
|
〇
|
- 高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組
|
〇
|
|
既存事業の「発展」
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
その他取り組み
|
|
×
|
|
|
×
|
|
|
×
|
経営展開サポート事業の対象となる事業は、既存事業の「深化」または「発展」につながる事業です。
既存事業の「深化」に該当するのは、経営基盤の強化に向けて既に営んでいる事業自体の質を高めるための取り組みです。事業内容や取り扱う商品を変更するのではなく、設備導入による業務の効率化や既存の商品やサービス等の品質向上につながる取り組みなどが当てはまります。
既存事業の「発展」に該当するのは、経営基盤の強化に向けて既に営んでいる事業をもとに新たな事業展開を図る取り組みです。既存の商品を原料とした新たな商品の開発や、店頭販売のみだった既存商品を扱うECサイトを新たに構築する取り組みなどが当てはまります。
既存事業の「深化」や「発展」に該当しないその他の取り組みは、経営展開サポート事業の助成対象外です。既存事業との関連性が認められない事業や単なる老朽設備の維持更新など、経営展開サポート事業の目的と異なる事業では助成金を受け取ることができないことに留意しましょう。
対象者
経営展開サポート事業に申請するためには、対象者の要件を満たす必要があります。申請者の事業規模や事業状況が対象者の要件を満たしていない場合は申請ができないため、経営展開サポート事業への申請を検討している人はその前提を踏まえておきましょう。
【対象者の要件(一部抜粋)】
- 都内の中小企業者(個人事業主含む)であること
- 法人の場合は本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
- 個人事業者の場合は納税地が都内にあること
- 直近決算期の売上高が既定の要件を満たしていること
- 令和6年度の経営展開サポート事業において一度も交付決定を受けていないこと
- 社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと
- 同一の内容で国や自治体等のほかの助成を受けていないこと
対象者の要件のひとつとして、都内の中小企業者であることが挙げられます。中小企業の定義にあてはまる個人事業主も対象となりますが、中小企業であっても大企業が実質的に経営に参画している場合は対象外となります。
また、対象者の要件のひとつとして、直近決算期の売上高に関する要件が挙げられます。2019年の決算期以降のいずれかの決算期と比較して減少している、または直近決算期において損失を計上していることが条件として定められており、いずれの条件も満たしていない事業者は申請できません。
経営展開サポート事業には複数の要件が定められていますが、ひとつでも満たせない要件がある場合は申請ができません。対象者の要件は随時変更される可能性があるため、経営展開サポート事業への申請を検討している人は、申請する募集回の募集要項から要件をすべて満たしていることを確認しましょう。
対象経費
経営展開サポート事業に申請するためには、対象経費の要件を満たす必要があります。申請しようとする経費が対象経費の要件を満たしていない場合は申請ができないため、経営展開サポート事業への申請を検討している人はその前提を踏まえておきましょう。
【経営展開サポート事業の対象経費】
|
項目
|
概要
|
対象例
|
|
原材料・副資材費
|
製品やサービスの改良等に直接使用する原材料、副資材、部品等の購入に要する経費
|
等
|
|
機械装置・工具器具費
|
製品・サービスの改良等に直接使用する機械や工具等を新たに購入・レンタルする際に要する経費
|
等
|
|
委託・外注費
|
自社内で直接実施することができない製品やサービス改良の一部を外部の事業者等に依頼する経費
|
等
|
|
産業財産権出願・導入費
|
- 改良等をした製品・サービスに係る権利等の出願に要する経費
- 権利等を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受ける場合に要する経費
|
以下の出願や譲渡等に要する費用
|
|
規格等認証・登録費
|
- 改良等をした製品・サービスの規格認証や登録に要する経費
- 規格等認証・登録に係る外部専門家の指導等を受ける場合に要する経費
|
- 認証・検査機関への申請手数料
- 成績証明書発行手数料
- 審査費用
- 登録証発行料
- 登録維持料(初回のみ)
- 翻訳料
- マニュアル整備等の指導及び作成代行
- 外部研修の受講料
- その他研修・教育費用
- 外部専門家の旅費交通費
等
|
|
設備等導入費
|
取組に直接必要な設備・備品等の購入費及びそれらの設置工事等に直接必要な経費
|
- 設備・備品等の購入費
- 直接仮設費(足場代、養生費等)
- 労務費
- 電線やケーブル等の材料・運搬費
- 搬入・据付費
- 撤去費
- 処分費
等
|
|
システム等導入費
|
取組に直接必要なシステム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、クラウド利用等に要する
経費
|
- システムの構築・改修に要する経費
- ソフトウェアの購入・利用に要する経費
- ハードウェアの購入・改修、リースに要する経費
- クラウドサービスの利用に要する経費
- 外部の事業者に設定等を依頼する場合に要する経費
- 助成対象期間に実施する運用・保守に要する経費
|
|
専門家指導費
|
取組について外部の専門家から専門技術等の指導・助言を受ける場合に要する経費
|
等
|
|
不動産賃借料
|
取組に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
|
(敷金、礼金、手数料、保険料等は対象外)
|
|
販売促進費
|
助成対象商品の販売促進に要する経費
|
- WEBサイト制作・改修費
- 印刷物製作費
- PR動画製作費
- 広告費
- 出展小間料
- 資材費
- 輸送費
- 通訳費
- オンライン出展基本料
- ECサイト出店初期登録料
|
|
その他経費
|
取組に直接必要な経費で、他の経費区分に属さないもの
|
–
|
経営展開サポート事業の対象経費には、「原材料・副資材費」「機械装置・工具器具費」など11の経費区分が定められています。「その他経費」では、他の経費区分に該当しないものの事業の取り組みとして必要であると認められる経費が助成対象となる場合があります。
ただし、対象経費に該当する項目であっても助成対象と認められない場合もあります。助成事業に直接関係のない経費や、契約から支払いまでの手続きが助成対象期間内に行われなかった経費などは、対象経費の項目に該当する内容であっても助成対象外となります。
なお、「販売促進費」および「その他経費」は単独での申請ができません。販売促進費とその他経費を申請したいと考えている人は、ほかの区分に該当する経費とあわせて申請しなければならないことに留意しておきましょう。
助成率と助成上限額
経営展開サポート事業では、最大800万円の助成金を受け取ることができます。経営展開サポート事業においていくらの金額を受け取れるのかは「助成対象経費」「助成率」「助成上限額」を用いて算出します。
【経営展開サポート事業の助成率と助成上限額】
|
助成率
|
助成対象経費の2/3以内
|
|
助成上限額
|
800万円
|
受け取れる助成金を算出するには、まずは申請する助成対象経費の金額を求めます。「機械装置・工具器具費」200万円と「委託・外注費」100万円を申請する場合「200万円+100万円=300万円」の計算式により300万円が助成対象経費の金額となります。
つぎに、対象経費の合計金額に助成率「2/3」を掛けます。助成対象経費が300万円の場合「300万円×2/3=200万円」となり、200万円を申請できる計算となります。
最後に、算出した金額が助成上限額を超えていないかどうかを確認します。経営展開サポート事業における助成上限額は「800万円」のため、助成対象経費に助成率を掛けて算出された金額が200万円であれば助成額の範囲内であるため、200万円を助成金として受け取れる計算です。
ただし、算出した金額が助成上限額である800万円を超える場合には、上限額の800万円までの支給となります。「助成対象経費×2/3」と「助成上限額」のうち、いずれか低い方の金額が申請金額として適用されます。
なお、実際に受給できる金額は助成事業の実施後に行う「実績報告」の内容に応じて決定されます。計算式によって求められるのは受給できる最大の金額であり、助成事業の実施内容によっては算出した金額よりも減額される可能性がある点に留意しましょう。
申請方法はJグランツによる電子申請
経営展開サポート事業への申請方法は、デジタル庁が運営する補助金や助成金の申請システム「Jグランツ」からの電子申請です。自治体の窓口での申請や郵送による申請は受け付けていないため、経営展開サポート事業へ申請予定の人はその前提を踏まえておきましょう。
経営展開サポート事業へ申請するためにはJグランツへログインし、申請フォームへ必要事項の入力を行います。入力する内容には「事業形態」「法人名(屋号)」「所在地」「代表者情報」「担当者情報」「事業実施場所」など複数の項目があり、申請者が法人か個人事業主かによって入力項目が異なります。
Jグランツは申請手続きのほか、申請内容の変更手続きや交付決定通知の確認など、経営展開サポート事業においてさまざまな場面で利用するサービスです。経営展開サポート事業の公式サイトでは、Jグランツの使い方が記載された「電子申請マニュアル」も公開されています。
なお、Jグランツへのログインには、さまざまな行政システムへログインできる共通アカウント「GビズID」のプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの発行には2週間程度を要する可能性があるため、経営展開サポート事業へ申請予定の人は余裕を持ってGビズIDを取得しておきましょう。
必要書類
Jグランツによる申請の際には、必要事項の入力に加えて必要書類の添付も行います。申請締め切りまでに書類が揃えられない場合は申請不可となり助成金を受け取ることができないため、事前にどのような書類が必要となるのかを確認しておきましょう。
【経営展開サポート事業の申請における必要書類】
|
項目
|
必要書類
|
|
全員が提出する書類
|
|
|
法人のみが提出する書類
|
- 履歴事項全部証明書
- 法人事業税納税証明書
- 法人都民税納税証明書
- 決算書(損益計算書)
|
|
個人事業主のみが提出する書類
|
- 開業届
- 個人事業税納税証明書
- 所得税納税証明書(※非課税の場合)
- 住民税納税証明書
- 住民税非課税証明書(※非課税の場)
- 所得税確定申告書
|
|
申請内容によって提出が必要となる書類
|
- 見積書(相見積書)
- 見積限定理由書
- カタログ
- 図面(設計図、平面図等)
- 特許証、特許等公報等
- 展示会出展要項
- ECサイトの出店登録要項
|
必要書類には「申請様式」「誓約書」「納税証明書」「決算書」「確定申告書」「見積書」など複数の種類があります。申請者が法人か個人事業主かによって用意すべき書類が異なるほか、申請内容に応じて該当者のみに必要となる書類もあります。
また、必要書類はすべて電子データとしてJグランツの申請フォームへ添付します。スマートフォン等を用いて撮影した写真を提出することも可能ですが、文字が鮮明に読み取れないものやデータ形式が規定を満たしていないものなどは不受理となるため、提出前に不備がないかどうかを確認してください。
なお、必要書類の中には自治体の役所や税務署、取引先など外部への発行依頼が必要となるものもあります。申請の際にはすべての書類を揃えておく必要がありますが、書類によっては即日発行ができない可能性もあるため、必要書類の準備は余裕を持って行いましょう。
審査項目
Jグランツの申請フォームへ入力した内容と提出書類をもとに、専門家による審査が行われます。審査には書類審査と面接があり、いずれも「発展性」「市場性」「実現性」「優秀性」「自己分析力」の5つの視点から採択または不採択を判断されます。
【審査の視点】
|
項目
|
詳細
|
|
発展性
|
既存事業の深化・発展に資する取組か
|
|
市場性
|
ポストコロナ等における事業環境の変化前後の市場分析は十分か
|
|
実現性
|
取り組むための体制は整っているか
|
|
優秀性
|
事業者としての創意工夫、今後の展望はあるか
|
|
自己分析力
|
自社の状況を適切に理解しているか
|
まずは、書類審査によってJグランツの入力内容と提出書類の内容が一定の水準を満たしているかどうかが審査されます。一定の水準を満たしていると判断された場合は面接日程・実施場所等がメールにて通知されますが、一定の水準を満たしていないと判断された場合は不採択となり不採択通知が届きます。
つぎに、書類審査を通過した申請者には専門家との対面による面接が実施されます。面接では申請書類をもとに内容の説明を行うこととなり、事業者の代表者、役員、従業員に限り最大2名までの出席が認められています。
審査結果は、申請もしくは面接実施からおおむね1ヶ月以内に通知されますが、申請の件数や内容により前後する可能性があります。メールの確認漏れにより面接に参加できなかった場合は申請の辞退とみなされるため、申請後は折を見てメールを確認しましょう。
なお、これまでの公募回における採択結果や採択率、採択事例などは2024年8月現在公表されていません。過去の採択率は審査の難易度や採択の傾向を知る手がかりのひとつとなるため、採択率の求め方や他の補助金や助成金の採択率を知りたい人は「補助金の採択率とは?」の記事を参考にしてみてください。
申請から助成金交付までの流れ
経営展開サポート事業への申請を検討している人は、申請から助成金交付までの流れを確認しておきましょう。全体の流れを確認することにより「助成金を受け取るためにはどのような手続きが必要となるのか」「助成金の入金がいつごろ行われるのか」など、制度の全体像をイメージできます。
【申請から助成金交付までの流れ】
|
流れ
|
詳細
|
|
①申請の提出
|
Jグランツによる電子申請を行う。
申請フォームへの入力と必要書類の添付が必要となる
|
|
②審査
|
申請内容をもとに書類と面接による審査が実施される
|
|
③交付決定
|
面接を通過した場合「交付決定通知書」がメールで送付される
|
|
④助成事業の実施
※アドバイザー派遣(任意)
|
申請した助成対象経費を用いて助成事業を実施する(交付決定日から1年間)
|
|
⑤実績報告
|
助成事業の完了後、原則1か月以内に実績報告書と必要書類を全て提出する
|
|
⑥完了検査
※アドバイザー派遣(必須)
|
実績報告の内容に基づき助成事業の実施が適正であるか審査され、助成金の交付額が決定する
|
|
⑦助成金額の確定
|
完了検査後約1か月後に「助成金確定通知書」により確定した交付額が通知される
|
|
⑧助成金の請求
|
「助成金確定通知書」の受領後「助成金請求書」を提出する
|
|
⑨助成金の入金
|
「助成金請求書」の提出から約1か月後に、指定の助成事業者名義の金融機関口座に助成金が入金される
|
経営展開サポート事業での助成金交付までの流れにおいて、まずは申請を行い助成金の目的に沿った事業計画であることを認められる「交付決定」を受ける必要があります。交付決定を受けるには、書類と面接による2つの審査を通過しなければなりません。
交付決定を受けた場合は、申請した経費を用いて事業計画に沿った助成事業を実施します。経営展開サポート事業において助成金の振込は助成事業の実施後となるため、助成対象期間中に経費を支払う際には自己資金による立替が必要です。
助成事業が完了したら、実績報告と完了検査を経て助成金額が確定し、諸手続きを実施したあと約1か月程度で指定の口座に助成金が振り込まれます。最終的な助成金額は助成事業の実施状況や完了検査の結果等に基づいて決定するため、助成金申請額よりも減額となる可能性があります。
なお、経営展開サポート事業では最大2回の「アドバイザー派遣」が実施され、助成事業の実施場所や帳簿の確認のほか、経営アドバイザーによる助言を受けることができます。助成事業期間中のアドバイザー派遣は任意ですが、助成事業の効果的な実施のため必要に応じて利用してみましょう。
2024年度における募集スケジュール
経営展開サポート事業の申請を検討している人は、2024年度における公募スケジュールを確認しておきましょう。経営展開サポート事業の公式サイトでは、2024年度に実施予定となっている第12回までの募集スケジュールが公開されています。
【経営展開サポート事業の募集スケジュール】
|
募集回
|
申請受付期間
|
|
第1回~第5回
|
受付終了
|
|
第6回
|
令和6年9月2日から9月13日まで
|
|
第7回
|
令和6年10月1日から10月15日まで
|
|
第8回
|
令和6年11月1日から11月15日まで
|
|
第9回
|
令和6年12月2日から12月13日まで
|
|
第10回
|
令和7年1月6日から1月15日まで
|
|
第11回
|
令和7年2月3日から2月14日まで
|
|
第12回
|
令和7年3月3日から3月14日まで
|
令和6年8月時点において、第5回までの受付が終了しています。今後のスケジュールは、令和7年3月に実施される第12回募集まで1か月に1度のペースで募集が行われる予定となっています。
また、第5回締切では予定されていた締め切り日よりも早く受付が終了されました。募集状況によっては予定よりも早く申請が締め切られる場合があるため、経営展開サポート事業へ申請したい人は余裕のあるスケジュールで準備ができる募集回への申請を検討しましょう。
なお、第7回以降のスケジュールは予定であり、予算の都合等により募集予定が変更される可能性があります。申請受付期間外や募集終了後は申請の提出ができないため、申請前に公式サイトから最新の募集状況を確認してください。
経営展開サポート事業に関するQ&A
経営展開サポート事業に関して、申請者が疑問に思いそうな点や申請の際につまずきそうな点をQ&Aにまとめました。事務局へ問い合わせる前に自分で解決できる可能性があるため、経営展開サポート事業への申請にあたって疑問や不安がある人はQ&Aを確認してみましょう。
【経営展開サポート事業に関するQ&A】
|
質問
|
回答
|
|
複数回申請できますか?
|
交付決定を受けた場合は本年度内の申請はできません。
一方、申請が不受理・不採択となった場合は再申請が可能です
|
|
面接はオンラインでも可能ですか?
|
原則は対面形式です。
対面での実施が困難な事情がある場合は事務局までご相談ください
|
|
新紙幣に対応する券売機に更新・改修するための費用も対象となりますか?
|
既存事業の深化や発展に繋がる取組であれば対象となる可能性があります
|
|
不採択となった場合に理由を教えてもらえますか?
|
審査の内容や結果等へのお問い合わせには一切お答えできません
|
|
公的機関から納税猶予の特例を受けていても申請できますか?
|
住民税・事業税等に未納がある場合は申請できません
|
|
経費の支払い方法は決まっていますか?
|
助成事業者名義の口座からの振込払いが原則です。
ただし、振込払いが困難な場合「クレジットカード」「現金」「手形・小切手」での支払いが認められる場合があります
|
|
経費をクレジットカードで支払ったのですが、引落し日が助成対象期間を超えてしまいます
|
引落し日が助成対象期間を超える支払いはすべて対象外となります
|
参考:「助成金 募集要項(一般コース)」および「FAQ」|東京都中小企業振興公社
助成対象経費の支払いは金融機関の口座からの振込払いが原則ですが、振込払いが困難な場合に限り「クレジットカード」「現金」「手形・小切手」が認められる場合があります。振込払い以外の方法によって支払いをする場合、それぞれの支払い方法に定められた条件を満たす必要があります。
また、経費をクレジットカードで支払った場合には、引落し日にも注意が必要です。経費の支払いは助成対象期間内に完了させることが条件となっているため、購入日が助成対象期間内であっても引落し日が助成対象期間を過ぎてしまう場合には助成対象外となります。
経営展開サポート事業に関する疑問や不安は、申請者自身で解決できる場合があります。問い合わせの電話が混みあうことも考えられるため、申請にあたって気になることがある人は事務局へ問い合わせる前に、まずは公式サイト内の募集要項やFAQを確認してみましょう。
申請に不安がある人は認定支援機関に相談する
経営展開サポート事業の申請は事業者が自分だけで行うことも可能ですが、申請に不安がある人は認定支援機関に相談することを検討しましょう。認定支援機関に相談することにより、申請に関する相談や書類作成への助言などさまざまな場面において経営展開サポート事業の申請を支援してもらうことができます。
認定支援機関は中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関のことです。認定支援機関には「税理士」「公認会計士」「中小企業診断士」「商工会」「金融機関」などの機関が登録されており、それぞれ支援内容や得意分野が異なります。
経営展開サポート事業では最大2回のアドバイザー派遣の利用が可能ですが、経営改善に関する助言や助成事業をより効果的に実施するための助言が主な内容となります。伴走支援として手厚いサポートを受けたい場合は、認定支援機関へ相談することも選択肢のひとつです。
認定支援機関に相談することにより、申請の不安を解消することや採択の可能性を高めることが可能です。補助金や助成金の相談ができる支援機関を詳しく知りたい人は「補助金の相談は誰にする?相談できる内容に合った相談先を解説」の記事を参考にしてみてください。
まとめ
経営展開サポート事業とは、ポストコロナにおける消費者ニーズの変化や物価・エネルギー価格の高騰などに対応するため、これまで営んできた事業を「深化」「発展」させて経営基盤の強化を図る取り組みを支援する制度です。2024年度に東京都が実施する助成金制度であり、中小企業や個人事業主が対象となります。
経営展開サポート事業では「原材料費」「機械装置費」「委託・外注費」「販売促進費」「その他経費」など、幅広い経費が助成対象です。助成率は助成対象経費の2/3以内であり、最大800万円を助成金として受け取ることができます。
ただし、助成金を受給するには書類と面接による審査に通過する必要があるほか、助成金が交付されるまでの自己資金が必要となることなど、いくつかの注意点もあります。申請すれば必ずもらえるものではない点や、支払いから助成金の受け取りまでに1年以上かかる可能性がある点に留意してください。
なお、2024年度においては令和7年3月に実施される第12回公募まで1か月に1度のペースで募集が行われる予定です。予算の都合や応募状況により募集スケジュールが変更になる可能性があるため、経営展開サポート事業への申請を検討している人は募集回の受付期間を確認し、余裕を持って準備を行いましょう。