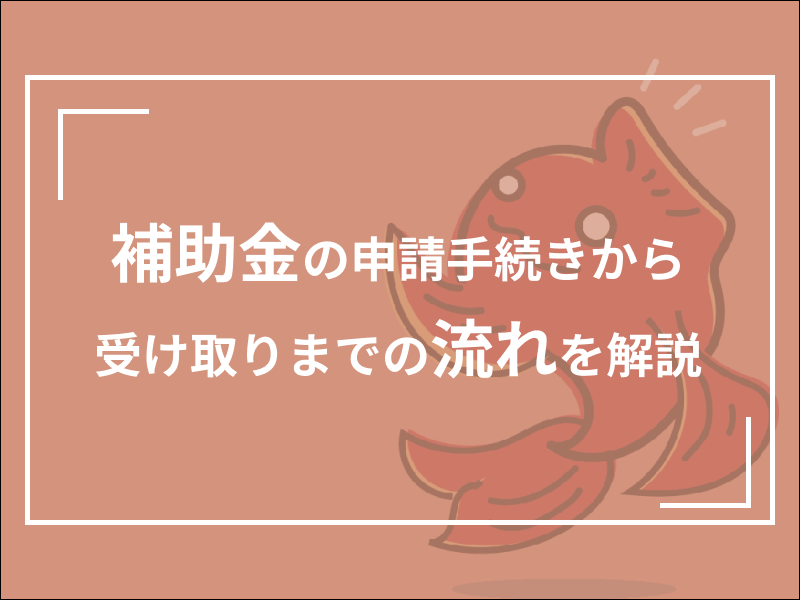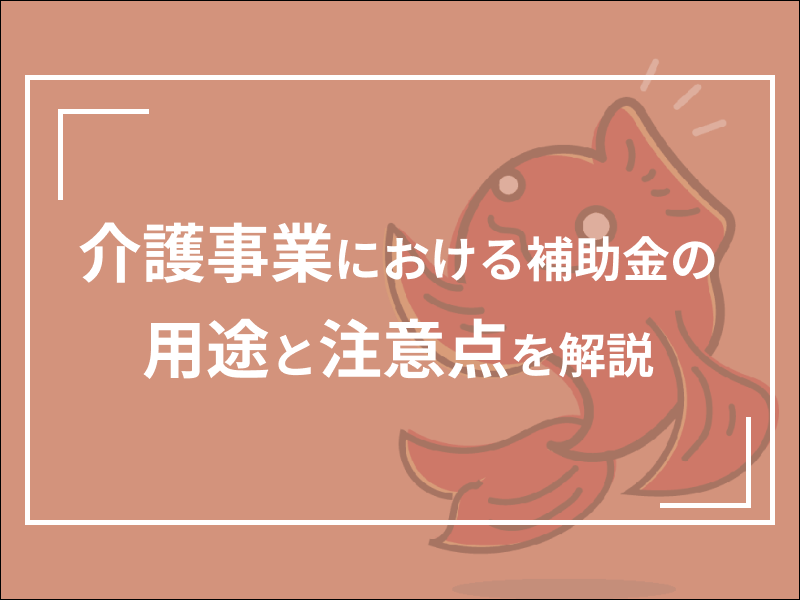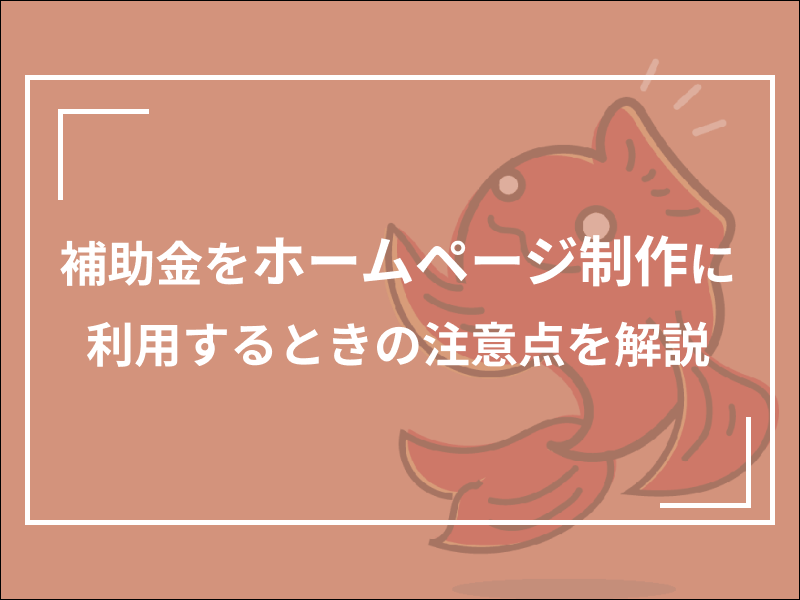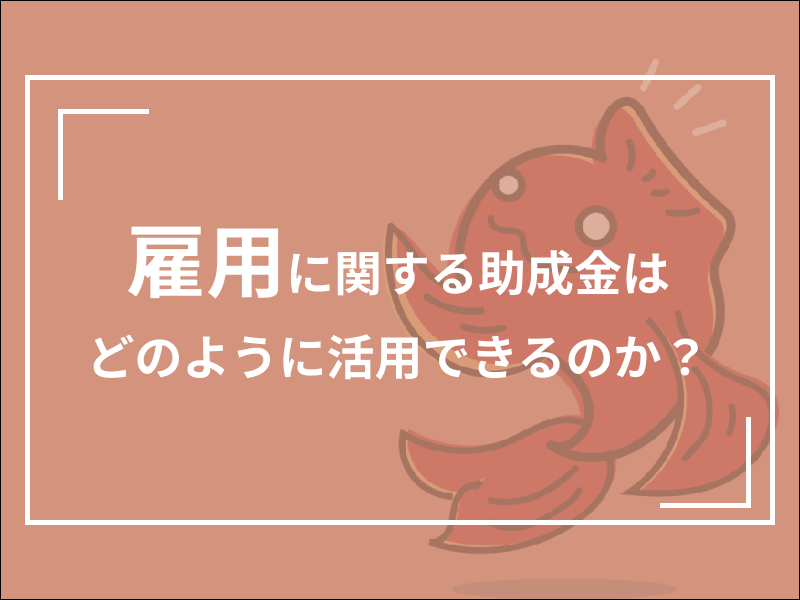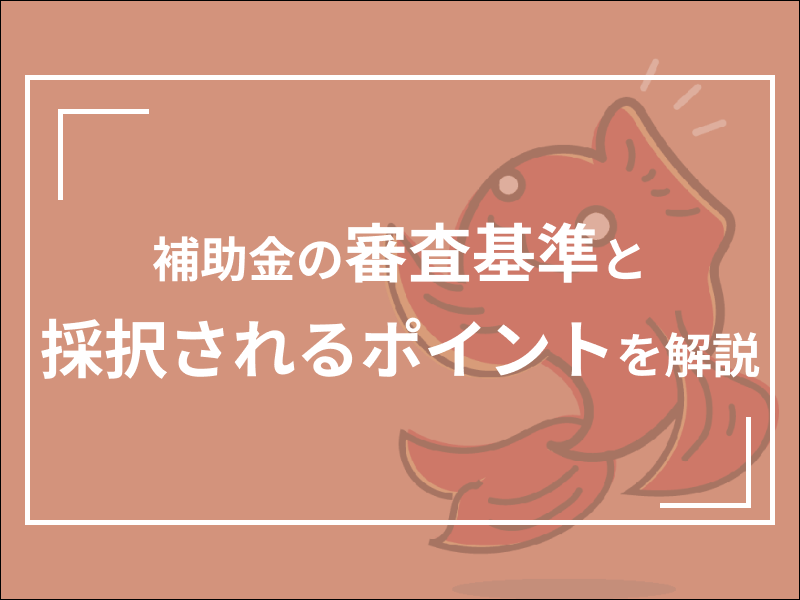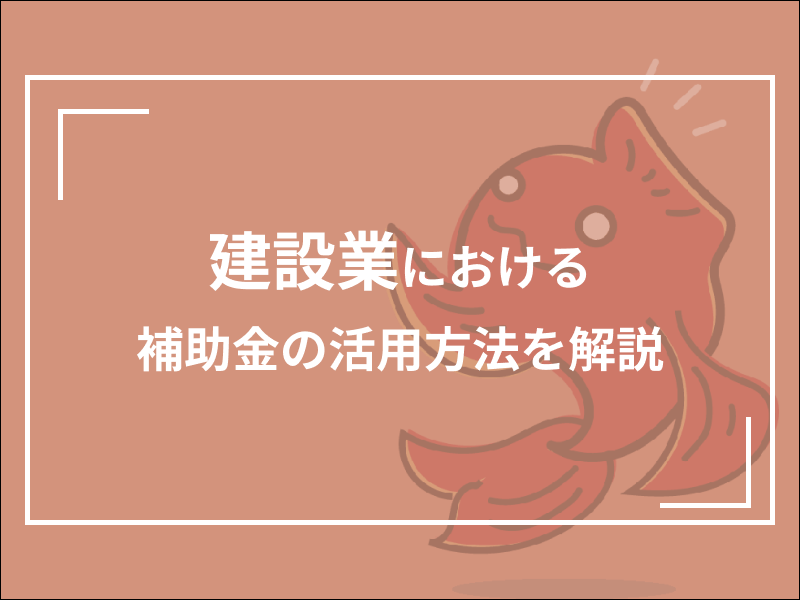補助金の申請条件を解説
補助金には、申請する際に満たすべき条件があります。補助金の申請条件の内容を知っておくことで、支援制度を利用する目的に合った補助金が見つかりやすくなります。
当記事では、補助金の申請条件を解説しているため、補助金の利用を検討している人は参考にしてみてください。
なお、当記事では事業者向けの補助金における申請条件の傾向を解説しています。個人向けの補助金とは申請条件が異なることを留意しておきましょう。
補助金の申請条件
補助金を申請するには、制度ごとに定められた条件を満たさなければなりません。申請条件を満たしていない事業者は、補助金へ申請できない場合や、申請しても不採択となる場合があります。
【補助金の申請条件の例】
- 申請者の条件
- 事業の条件
- 経費の条件
補助金には「申請者」「補助事業」「経費」のそれぞれの項目に、補助対象となるための「申請条件」が定められている傾向にあります。申請条件には対象外となる条件が定められている場合もあり、対象外となる項目に該当した際は申請条件をすべて満たしても補助対象者として認められません。
また、補助金によっては申請枠が分けられ、申請枠ごとの追加条件が設けられている場合があります。申請者全員が満たさなければならない申請条件に加え、適宜申請枠の追加条件を満たす必要があります。
なお、補助金制度はすべての申請条件を満たしていても、必ず補助金を受け取れるとは限りません。補助金には書類審査があり、提出書類の審査によって採択されることで補助事業を実施することができます。
申請者の条件
補助金を申請するには、応募する制度の補助対象者の条件に該当しなければなりません。申請者の条件を満たしていない場合、その補助金には応募することができないからです。
【申請者の条件の例】
- 定められた事業規模の範囲内であるか
- 定められた職種に該当しているか
- 定められた資本金の額の範囲内であるか 等
補助金の対象となる申請者の条件には「事業規模」が定められている場合があります。個人事業主や小規模事業者が対象の補助金に大企業が申請しても、対象外となる可能性があります。
また、申請者となる条件には「日本国内で事業を営む事業者」と定められている場合があります。日本国内に本社を有するまたは日本国内で事業を営む事業者であることが、申請者の条件となっている傾向にあります。
補助金は制度それぞれに申請者の条件が設定されています。補助金の活用を検討している場合は、自社が利用できる制度であるかどうか確認する必要があります。
対象外となる申請者
申請者の条件を確認した事業者は、対象外となる条件も確認しておきましょう。申請者の条件をすべて満たす事業者であっても対象外となる条件に当てはまる場合があり、対象外となった申請者は応募できないからです。
【対象外となる申請者の条件の例】
- 任意団体
- 不正行為を行った事業者 等
対象外となる申請者の条件として「任意団体」が挙げられます。補助金によっては、町内会やサークルなどの法人格のない任意団体が補助対象外に該当する場合があります。
また、対象外となる申請者の条件として「申請時に不正行為を行った事業者」が挙げられます。不正行為を行ったことが発覚した場合、不採択になるほか次回以降の補助金の申請ができない可能性があることを留意しておきましょう。
なお、補助金によっては申請時点で開業していない創業予定者が対象外となる傾向にあります。事業者向けの補助金には、創業予定者が利用できる補助金もあるため、自社が利用できる補助金を探してみましょう。
事業の条件
補助金を申請するには、補助対象事業の条件を満たす必要があります。補助事業に取り組む目的や条件が、補助金が定める目的や条件と一致していない場合、申請しても不採択となってしまう可能性があるからです。
【補助対象事業の条件の例】
- 補助金の目的や趣旨と一致していること
- 事業計画書を申請者自ら作成し取り組むこと 等
補助金には制度ごとに「販路開拓」や「業務効率化」などの目的が定められています。補助事業が、補助金の目的に合っていないと判断された場合は、不採択となります。
また、事業計画を申請者自ら作成し取り組むことが事業の条件として挙げられます。申請者自らが検討していなかったことが発覚した場合、補助金の目的や趣旨に沿っていないと判断され、ほかの審査項目で高い評価を得ていても不採択となる場合があります。
なお、補助金の目的に沿った取組内容のイメージがわかない事業者は、過去に採択された事例を探してみましょう。補助金によっては、公式サイトなどに具体的な取組事例が掲載されている場合もあるため、事業計画をたてる際の参考にすることができます。
対象外となる事業
補助金の対象外となる事業を行っていた場合、補助金に申請することはできません。補助金に申請する場合、対象外の事業に該当していないか確認する必要があります。
【対象外となる事業の条件の例】
- 公的な支援を行うことが適切でないと判断される事業
- 他の支援制度と重複して申請する事業
- 補助金の目的や趣旨と合っていない事業 等
補助金の対象外となる事業として挙げられるのは「公的な支援を行うことが適切でないと判断される事業であること」です。補助金では、公序良俗に反する事業などを営む事業者は支援を行うことが適切でないと判断され、補助対象外となる傾向にあります。
また、補助金の対象外となる事業として挙げられるのは「他の支援制度と重複して申請すること」です。申請する補助金以外の国などが支援する他の制度と併用することは認められていない場合があります。
なお、補助金ごとに対象外となる事業の条件は異なります。申請条件を満たしても対象外の事業と判断された場合は補助金が支給されない可能性があります。
経費の条件
補助金には、補助対象経費の条件があります。条件を満たさなければ経費として認められないため、補助金の申請時に経費として計上していても、対象外と判断された経費に対する補助金は支給されません。
【経費の条件の例】
- 指定の経費項目に該当する経費
- 使用目的が補助事業に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発注等が発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 等
たとえば、「指定の経費項目に該当する経費」であることが経費の条件として挙げられます。補助金の経費項目に該当しないと判断された場合は、補助対象外となるため、申請した経費がすべて補助対象になるとは限りません。
また、「補助対象期間中に支払が完了した経費」であることが経費の条件として挙げられます。交付決定日以降に契約や依頼などを行い、補助対象期間中に事業を実施して支払が完了した経費のみが補助対象として認められます。
なお、経費の使用目的が補助事業の遂行に必要なものであると認められなければ、補助対象から外れてしまう可能性があります。対象経費の条件を満たしていても、補助事業と関連性がない経費に対し補助金は支給されないことを留意しておきましょう。
対象外となる経費
補助金には対象外となる経費があるため、補助対象経費を確認した申請者は対象外となる経費の条件も確認しておきましょう。補助金によっては、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、不採択となる傾向にあるからです。
【対象外となる経費の条件の例】
- 汎用性のある経費
- 事務用品等の消耗品代
- 補助金申請の書類作成費 等
補助金の対象外となる経費として挙げられるのは、「汎用性のある経費」です。パソコンや車といった補助事業以外でもさまざまな用途で利用できる経費などは対象外となる場合があります。
また、補助金の対象外となる経費として挙げられるのは、「補助金申請の書類作成費」です。補助金の目的と関連性がない経費は補助対象として認められない可能性があるため対象外となる場合があります。
なお、補助金によっては導入する機器の種類が制限されている場合があります。申請を検討している経費が補助対象外に該当していないか確認する場合は、補助金の公式サイトに記載されている問い合わせ先に相談してみましょう。
申請条件を押さえた事業者は審査内容も確認しておく
補助金の申請条件を抑えた事業者は、審査内容も確認しておきましょう。補助金には審査があり、審査で採択されないと補助金を受け取ることはできないからです。
補助金の書類審査では、申請者が提出した申請書類によって、補助金の対象となる申請者であるかどうかを確認されます。申請条件を満たしていることに加えて「審査項目」「加点項目」を満たしていることを審査によって判断されます。
また、補助金によっては、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて実施される「口頭審査」が行われる場合があります。口頭審査では、オンライン形式の面接にて申請者自身の事業計画に対する理解度が確認されます。
なお、補助金の審査で採択されても、申請した金額を全額受け取れるとは限りません。取組を終了した後に提出する書類により、補助金額を決定する審査が行われ、取組を適切に行ったと判断されると実際に受け取れる金額が決まります。
まとめ
事業者向けの補助金には申請条件があります。補助金を申請するには、制度ごとに定められた条件を満たさなければなりません。
補助金の申請条件の例として申請者や補助事業、経費に条件が設定されている場合があります。対象外となる条件もある場合があるため、申請する公募要項の要件をよく読み込むことが重要です。
また、補助金には書類審査があり、審査で採択されないと補助金を受け取ることはできません。補助金の利用を検討している事業者は、申請条件を満たせられる補助事業の目的に合った補助金を探しましょう。